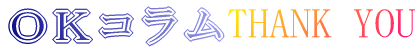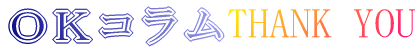| 標高が高い(山の上)程、気温が低くなるのはなぜ? |
|
|
山に登る人は自然に感じているとは思いますが、山の上の方が
太陽が近いはずなのに気温が低くなります。なぜ、太陽が近くなる
にも関わらず、気温が低くなるのでしょうか?
早速、その原因をまとめてみました。下図をみて下さい。
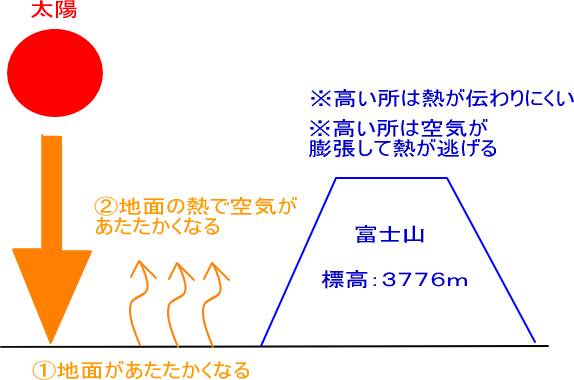
上の図のように気温は地面が温められ、地面の熱が
空気に伝わる事で気温が上昇します。その為、標高が高い山では
地面の熱が伝わりにくくなる為、気温は低くなります。
山の上では、地表で太陽光に温められた空気も、
周囲の冷たい空気によって冷やされる為、気温は低くなります。
また、標高が高い程、気圧が低くなり、空気が膨張する為、
熱エネルギーも弱くなり、気温が下がります。(シャルルの法則)
※標高と気温の関係ですが、標高が100m高くなるごとに
気温が0.6℃ずつ低下すると言われています。
例えば、富士山のふもとの気温が30℃だとしても、富士山山頂
での気温は約8℃という事になります。
※気圧とは・・・空気の重さ(1リットルあたり1.29g)による圧力
の事を言い、地表付近の大気圧は
1気圧=1013hpa(ヘクトパスカル)=約1kg重/cm2となって
います。これが標高3500m付近では659hpa=約0.65気圧
となります。つまり、標高が高い所では気圧が低くなる為、
気温が低くなります。
※シャルルの法則とは・・・圧力が一定のとき、理想気体の体積は
絶対温度に比例することを示した法則の事を言います。
1787年にジャック・シャルル(フランス人)が発見し、1802年に
ジョセフ・ルイ・ゲイ=リュサック(フランス人)によって初めて発表されました。 |
|
|
| mixiチェック
|
| 科学に関する豆知識一覧 |
|