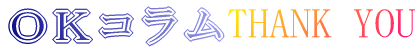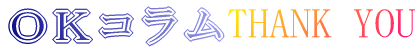以前、光は何でできているかというコラムを書いた事がありましたが、
その照明等で光を発生させる電気は何でできているのでしょうか?
電気を知る為にまず電子と電荷を知りましょう。
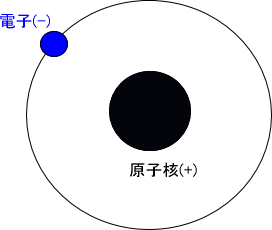
物質を構成する最小単位は原子ですが、
原子は中心となる原子核と、その周囲を回転する電子から成り立っています。
原子核の中にある陽子はプラス、電子はマイナスの電気を帯びています
(帯電状態)。
この帯電状態の物質は電荷(でんか)を持つといい、
その大きさの単位はQ(クーロン)といいます。
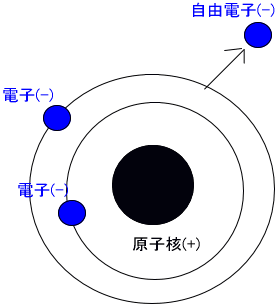
多くの物質では陽子も電子の数は一定で、
電子は原子核の周囲を回転するだけですが、
何かの拍子に軌道を離れる場合があります。
この軌道を離れた電子を自由電子といいます。
この自由電子の流れが電気の流れ(電流)となります。
では次は、自由電子の流れを説明しましょう。
導体の中に電子(自由電子)が入ってくると、
その物質の電子を押しのけるのです。
すると押しのけられた電子は別の電子を押しのけます。
野球で満塁のところ打者がヒットを放って一塁へ、
それまで一塁にいたランナーは二塁、二塁にいたランナーは三塁、
三塁にいたランナーはホームベースへ移動するようなものです。
導体と絶縁体
電気を通しやすい物体を導体・電気の通しにくい物体を絶縁体と言います。
導体とはこの電子が軌道を離れやすい物質(自由電子になりやすい電子が多い)で、
絶縁体とはこの電子が他の電子を押しのけにくい、
いいかえれば原子核と電子の結びつきが強力な物質(自由電子になりにくい)を指します。
導体・・・鉄、アルミニウム、金、銀、銅、ステンレス
絶縁体・・・ビニール、プラスチック、ゴム、ガラス
電流と電力と電力の関係
先程、述べた通り、電子の流れが電流ですが、
この電子を引きつける力を電力といいます。
電気はよく水車に例えられます。
①水の流れる量が電流(A:アンペア)です
②水の流れる速さが電圧(V:ボルト)です。
③水車を回せる回数が電力(W:ワット)です。
電力(W)=電流(A)×電圧(V)となります。
つまり、電流=電力÷電圧、電圧=電力÷電流となります。
(1秒間に対する値です。) |